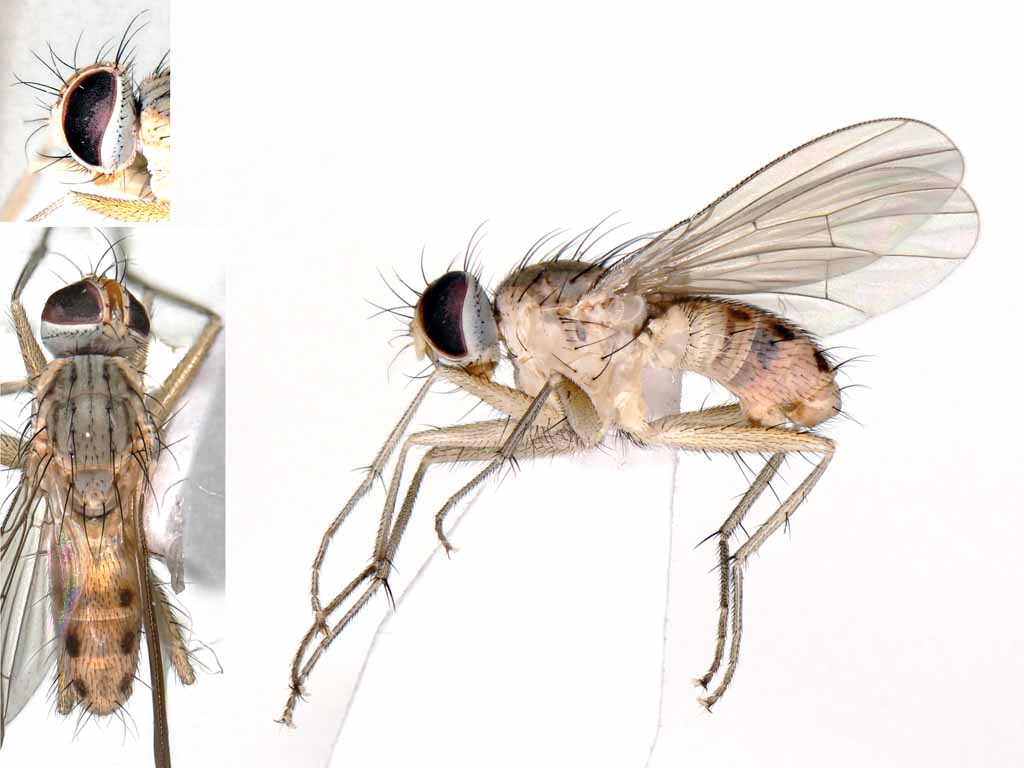|
サーバーの障害で昨日アクセスできなかった方がいたのではないかと思います。
ご迷惑をお掛けしましたがすみませんでした。無事復旧しましたので、またよろしくお願いいたします。 話は変わりますが、ハエ男は無事出稼ぎを終了し、本日飯田に帰還します。 連絡先は変わらずfurumusiと(@aez.jp)です。 談話会会員の皆様は4/4に大阪でお会いしませう。
ハエ男様.
また,データが全部消えたのではないかと不安でした. 大阪で会いましょう. |
|
ヒメガガンボ科に属する
Erioconopa elegantula (Alexander, 1913) だと思います。
達磨様、ありがとうございます。
Erioconopa elegantula (Alexander, 1913)で検索しても日本語のページでは何も出てきませんでした。良く似た学名の イツモンヒメガガンボ, Erioptera (Erioptera) elegantula, Alexander. 1913 というのを見つけましたが、この種の情報も多くは無いように思います。 何年も前にガガンボのことを詳しく紹介していたサイトがあったのですが、最近はそれが見つかりません。どこかの大学関係のサイトだったような記憶があるのですが、あのようなサイトが復活するとガガンボも分かりやすくなるのになあと思います。
田中川様.
ガガンボ関連は,Catalogue of the Craneflies of the World http://nlbif.eti.uva.nl/ccw/index.php で学名を入れるとシノニム等も簡単にわかります. ちなみに,Erioptera elegantulaとして記載された種類が,現在でErioconopa elegantulaという学名になっているようです. 九大のサイトにあった大蚊天国は,とある学生が卒業して消えてしまったようです.(昨年より改名して開店しましたが,種名リストは無いようです.) 同じく九大のヤドリバエのサイトも,教授が定年になって消えてしまいましたね. また,北大にもキノコバエのサイトがあったのですが,これも消えてしまいました. このような有用なサイトは,国が保管するとかしてくれると良いのですが;^_^)
茨城_市毛様、ありがとうございます。
イツモンヒメガガンボだったんですね。図書館へ行って調べてきます。 有用なサイトは本当に残したいものですね。作るのは大変な労力だったでしょうに。大学での研究というのは学生や教授が去ると引継ぎや残していこうとする考え方が無さそうですね。 |
|
埼玉県昆虫誌のカノコヤドリバエの学名が九大目録と違うので
ネットを探ってみたら、ライプニッツ農業景観研究センターの ページに「ヤドリバエ科のシノニムリスト」 http://www.zalf.de/home_zalf/institute/dei/php/index.php?page=Tachinidae がありました。左側のTaxonがジュニアシノニム、im DEI(ドイツ昆虫学研究所)がシニアシノニムとなります。 カノコヤドリバエ Isocarceliopsis hemimacquartioides Baranov 1934 ↓ Carcelia ceylanica (Brauer & Bergenstamm 1891) となるようです。
セスジ様.
セスジ様が紹介している頁は,ライプニッツ農業景観研究センターの収蔵標本リストであって,シノニムリストとは位置付けが若干異なると私は思います.(ハナアブ科を見ると,1980年代頃の学名となっているようで,その後30年分のシノニム処置が反映されていないようです) さて,問題のカノコヤドリバエの学名ですが,埼玉県昆虫誌の出典である埼玉県動物誌(1978)では,カノコヤドリバエに Carcelia(Euryclea) ceylanicaの学名が当てられております. 当時は,既にShima(1969)で日本産Carcelia属について解説していますが,Carcelia(Carcelia) hemimacquartioides を収録する一方,C. ceylanicaの学名は見当たりません.(C. hemimacquartioidesのHostにAmata fortuneiカノコガと記されています) Mesnil(1968)の,A Preliminary List of Tachinidae from Japanでも,C. ceylanicaの学名は出てきません. そして,日本産昆虫総目録(1989)では,カノコヤドリバエはCarcelia(Euryclea) hemimacquartioidesとなっており,そ の後の皇居のヤドリバエ科(2000)等でも,同様の扱いとなっております. 一方,中国ハエ類(1999)のCarcelia(Euryclea) ceylanicaの項目にはシノニムは記されていません. なお,Herting(1984)Catalogue of Palearctic TachinidaeのAnnotationsには, (43) C. (E.)-hemimacquartioides Baranov is not a synonym of ceylanica Brauer & Bergenstamm (Eufischeria). The types of the two species (seen by me) differ markedly in the width of the frons and the shape of the third antennal joint. との記述があるので,何かの論文でシノニムとされたものが復活したのではないかと思います. そのようなわけで,次の日本産昆虫総目録が出るまでは,カノコヤドリバエの学名はCarcelia(Euryclea) hemimacquartioidesで良いのではないかと思います.
Shima (2006) A host-paratsite catalog of Tachinide (Diptera) of Japan, Makunagi/Acta Dipterologica, Supplement 2 によれば,カノコヤドリバエの学名は:
Carcelia (Euryclea) hemimacquartoides Baranov です.おそらくこれが本種の学名としては最新情報でしょう. 寄主はカノコガ(北海道帯広)だけで,種の分布は北海道,本州,九州;中国(北京,上海,台湾)と示されています(本文は英文). なお,本件とは無関係ですが,学名に人名を用いるときに,それに hemi, neo, para, nigri-, -oides などの接頭語や接尾語をつけるのは,一般に好ましいこととは言われていません.本種の場合には,Baranovは,接頭語に加えて接尾語までMacquartに付けたことになります.この場合,たとえ人名ではなくとも,余り感じのよい学名ではないでしょう.「何々に似たものの半分」と言うようなことで,さっぱり意味が通じません.
市毛様・アノニモミイア様
ご教授ありがとうございました。収蔵標本リストですね。 早とちりで申し訳ございません。 |
|
田中川様.
アシナガバエ科のSyntormon属の1種と思われます. 過去ログに何度か出ています.
田中川様
私も、市毛さんに賛成です。
茨城_市毛_有弁類整理中様、バグリッチ様、ありがとうございます。
どうやら属名まで判明すれば良しとしなければならないようですが、「アシナガバエ科 Syntormon」で検索をかけてもほとんど何も出てきませんが、Syntormon属って新しい属名なのでしょうか。 こちらにも出ておりませんが。 http://furumusi.aez.jp/wiki.cgi?%A5%A2%A5%B7%A5%CA%A5%AC%A5%D0%A5%A8%B2%CA
Syntormon属は1857年にLoewによって創設された属で、世界に100種余り生息し、ほぼ全世界に分布していますが、北半球の温帯に最も種が多いものです。私も中国の種を何種か新種として記載しましたが、日本産のものは未研究のまま放置状態です。あなたが写真で撮影されたとおり、雄の第3触角節(第1鞭小節)が著しく伸長して、これに第2節が食い込むようになっていること、雄交尾器は小型で目立たないこと、多くの種で雄の後脚の第1付小節にえぐれや特殊な剛毛を生じることなどが目立つ特徴です。
日本でも早春に多く、平地の庭に出た裸地の漏水場所などある程度恒常的な湿地にたむろして、驚かすと後脚を下に長く垂らしてゆっくりと飛翔します。時には家の中にも入ってきて、食卓の上などに静止していることさえあります。アシナガバエ科としては身近にいて、しかも大変おとなしい仲間です。 日本のアシナガバエ科は海浜岩礁性のものと、渓流性のDiostracusはかなり詳しく研究されましたが、他の属はほとんど全く研究されていない、という状況です。
三枝豊平様、いつもながら判りやすく説明していただき、ありがとうございます。
生息状況や生態についての解説もありがたい事です。 |
 2007年7月14日に北海道千歳市の広葉樹林で採集したものです。冬虫夏草に寄生されており、幼虫はミズナラの朽木の樹皮をめくると出てきました。体長は25ミリ程で無脚です。 2007年7月14日に北海道千歳市の広葉樹林で採集したものです。冬虫夏草に寄生されており、幼虫はミズナラの朽木の樹皮をめくると出てきました。体長は25ミリ程で無脚です。冬虫夏草図鑑ではこの幼虫を甲虫幼虫としていますが、http://yukipro.sap.hokkyodai.ac.jp/animal/i_02.html のキアブ幼虫の画像を見て双翅目の一種では?と思いました。 画像が不鮮明で申し訳ないですが、教えていただければ幸いです。
推定されたとおり,キアブ科Xylophagusの1種の幼虫であることはほぼ確実でしょう.
ありがとうございます。
幼虫図鑑にも全姿が載っていなかったので、教えていただけて助かりました。
この虫草の子実体(子嚢果のつぶつぶがついている部分)の写真は撮影していらっしゃいましょうか?
虫草にちょっと興味がありますものですから。
1枚目はキアブ属の1種でしょう.2枚目も双翅目でキアブらしいのですが,この画像だけではわかりません.3枚目はどちらが頭部かわからず,双翅目か鞘翅目か,幼虫か蛹かの見当がつきません.どうもパッとしないお答えです.
ありがとうございます。
昆虫をきれいにクリ−ンアップしなければなりませんでしたね。 このときは冬虫夏草をかじり始めてまもなくでしたので、菌類のほうにポイントを置いた写真になってしまいました。 3枚目のは恐らく虫体は右向きじゃないかと思いますが、今となっては確認がとれません。この場所では比較的多く見つかるので、そのうちに再確認しておこうと思っています。
pierisさんのご想像のとおり(?)画像の幼虫はサビイロクビオレタケに寄生されたものです。私の知る限りサビイロは必ずこの幼虫に寄生するようです。ホソエノアカクビオレタケも今まで多数観察してきましたが、脚のない蛆状の幼虫であり鞘翅目の幼虫ではないようです。
クチキフサノミタケの寄主は、所有する標本と幼虫図鑑をみたところゴミムシダマシ科幼虫でよいと思います。尾部に突起がある点でサビイロの寄主と似ていますが、しっかりと脚がついており無脚ではありません。
Kさまコメントをありがとうございます。
上の3種は共にブナの倒木からでした。 虫草と寄主との関係が大変面白いですね。 ハエヤドリタケはオオクロバエなどから出るのは完全型で、ムシヒキアブから出るのは不完全型のような気がします。クロバエの仲間とムシヒキアブの仲間は菌にとって条件が違うのかな、単に産地の違いかな、菌ははたして同一かなという疑問もありますね。いやはや面白いです。 |
 クロバエ科のMelinda pruinosaコチビクロバエとM. pusillaチビクロバエの違いが良く判りません. クロバエ科のMelinda pruinosaコチビクロバエとM. pusillaチビクロバエの違いが良く判りません.Fauna Japonica P.32を見ると,palpiの色が褐色なのでM. pusillaとなるようなのですが,交尾器を見るとM. pruinosaのようにも見えます.
Fauna Japonicaや、この記述のもと文献となったKurahashi(1964)ではpalpiの色は、M. pruinosaがblackish、つまり黒っぽく(黒色ということでないのがミソ)M. pusillaがbrownつまり褐色となっており、なおかつ"This species can be hardly differented from M. pruinosa by the external appearance."つまり、外見では(交尾器を見ない限り)同定困難とされています。基準となる比較用の標本がよほどたくさん蓄積され、個体変異の幅がつかめない限りは、palpiの色で同定しないほうがよく、交尾器の形態による判断を信じたほうがよいかと思います。
また、分類学的な変更もあるのでご注意ください。 Fauna JaponicaでMelindaに分類されていたハエは、イオコクロバエを除いてMelindaからははずされています。Melindaは亜科MELANOMYIINAEに分類されていますが、この亜科に属するハエはカタツムリ寄生で特殊化した産卵管を有していますが、Fauna JaponicaのMelindaでこの産卵管を有しているのはイオコクロバエだけです。 1979年の「ハエ−生態と防除−」ではイオコクロバエ以外のFauna JaponicaのMelindaはOnesiaに移されたとされていますが、コチビクロバエとチビクロバエは横溝後翅内剛毛が3本ではなく2本ですので、Knut Rongnesの分類に従えば、OnesiaではなくBellardiaになります。 さらにチビクロバエの原記載時の学名はMusca pusilla Meigen, 1826ですが、1790年にGmelinがMusca pusillaを記載しています(現在ハナアブ科に分類されている種らしい)ので、これのJunior primary homonymになってしまいます。そのため、Knut Rongesの"Blowflies (Diptera, Calliphoridae) of Fennoscandia and Denmark"ではOnesia viarum Robineau-Desvoidy, 1830を有効な原記載として、Bellardia viarum (Robineau-Desvoidy, 1830)を採用しています。
とりあえず♂ゲニの形状はコチビクロバエになると思います。
手元にシノニム関連の資料がないので学名の取り扱いは?つきますが中国動物誌 麗蝿科を見る限りはBellardia nartsukae=M. pruinosaになると思います。
ちょっと引っかかっている点が1つあります。
いろいろ検索してみても、Gmelinが1790年に記載している"pusilla"という種がどうしてもカメムシしか見つからないのですよね。Rongesの言うところのハナアブ科のMusca pusillaはどこに行ってしまったのでしょうか。
ウミユスリカ様.
確かに,色については難しいものですね. 交尾器での同定に自信が持てなかったのは,Kurahashi(1964)やFauna Japonicaでの古い分布記録と,埼玉県昆虫誌や皇居の昆虫での分布が逆転しているように感じたからです. Kurahashi(1964)やFauna Japonicaでは,M. pruinosaコチビクロバエが山岳部に分布し,M. pusillaチビクロバエは森林地帯や沼沢地の普通種と記されています. 一方,埼玉県昆虫誌ではM. pruinosaコチビクロバエが平地に分布し,M. pusillaチビクロバエが山岳部で記録されており, 皇居の昆虫でもコチビクロバエ M. pruinosaが記録されています. どちらの分布が合っているのでしょうかね? なお,学名については諸説があるようですが,次回の目録では両種ともOnesia属で,コチビクロバエはOnesia nartshukae (Grunin, 1970)となっていたのでは?
ハエ男.
返信を書いている間に,コメントが入ってしまいましたね. コチビクロバエとのことありがとうございます. ウミユスリカ様. Musca(Syrphus) pusilla Gmelin, 1790はSys. Nat. Ed.13で収録されたと記されていますが,旧北区のカタログではDoubtful species of Syrphidaeとの扱いになっています.
市毛様
Kurahashi(1964)をよく見ると、チビクロバエが標高2500mの高山にまで出現し、世界での分布も北に偏っている(北欧のデンマークにまで出現する)のに対し、コチビクロバエは山地に出現するものの比較的稀(つまり地点の例数が少なくなりがち)で、世界での分布も南に偏っている(北欧では記録されておらず、チビクロバエの記録がない北アフリカのチュニジアやアルジェリアに出現する)ことが読み取れます。「埼玉県昆虫誌」や「皇居の昆虫」の記述とは矛盾しないと思います。 >> 次回の目録では両種ともOnesia属で,コチビクロバエはOnesia nartshukae (Grunin, 1970)となっていたのでは? まだ公式には未発表のリストなので、あえてスルーしておきました。Onesia属とBellardia属は非常に縁が近いので、BellardiaとOnesiaを分けない見解なのだと推測しております。横溝後翅内剛毛の数と前縁脈の下面の毛の生えている範囲に違いが出るのですが、この辺りの形質の評価で見解が分かれるのかもしれません。 >> 旧北区のカタログではDoubtful species of Syrphidaeとの扱いになっています. なるほど。存在するか疑わしい種なのですね。
>> まだ公式には未発表のリストなので、あえてスルーしておきました。
と書きましたが、「埼玉県昆虫誌」で既にこの学名になっていましたね。今確認いたしました。 また、「中国蝿類」ではコチビクロバエがBellardia nartshukae (Grunin, 1970)、チビクロバエがBellardia pusilla (Meigen, 1826)となっていました。「中国動物誌 麗蝿科」では、Bellardia nartshukaeの方は掲載されていますが、チビクロバエは掲載されていませんでした。 どうも、Bellardia属を認めるか、またMusca pusilla Meigen, 1826を有効な記載とみなすかどうかがどの学名を採用するかの焦点となっているようですね。
ウミユスリカ様.
ネットを調べたら,もっと劇的な論文が出ていました. Verves(2004)The species of genus Bellardia Robineau-Desvoidy http://www.biosoil.ru/fee/2004/N-135/N-135.pdf この論文では,Melinda pruinosaとM. pusilla双方を誤同定としてBellardia nartshukaeのシノニムとしています. 分布を見る限り,極東側にはヨーロッパとは別の種類が 分布すると考えているようです. 私としては,双方の形態の差が少ないので,このほうがスッキリするような気にもします. ありがとうございました.
>> この論文では,Melinda pruinosaとM. pusilla双方を誤同定としてBellardia nartshukaeのシノニムとしています.
なるほど。でも、Bellardiaって世界的に見ても、雄でも(つまり交尾器をチェックしても)種間の形質の差異がわずかで、同定の難しさは札付きなんですよ。だから、コチビクロバエとチビクロバエが同種を無理に2種に分けてしまっていたのか、本当に別の2種なのかは、まだまだ検証研究が不足しているようにも思えます。 もっと微細な形質を徹底的に比較して、さらに最終的にはDNAバーコーディングなんかの手も借りる必要があるかもしれません。
おまけですが、RongnesはTriceratopyga(フタオクロバエ属)とAldrichina(ケブカクロバエ属)は認めていません。Calliphoraに統合しています。このあたりの属レベルの分類はまだ流動的ですね。
ウミユスリカ様.
確かに,有弁類は分類が流動的なところが多いようですね. 今年こそと有弁類の標本を整理していますが,和名を書いていると自分がイエバエ科を調べていたのかクロバエ科を調べていたのか判らなくなります. イエバエ科のなかには,○○ハナバエというのも多いですし;^_^)
>> 和名を書いていると自分がイエバエ科を調べていたのかクロバエ科を調べていたのか判らなくなります.
イエバエ科にキバネクロバエ、セアカクロバエ、オオセアカクロバエなんていうのがいますからね。ただ、後二者は小盾板を見れば、いかにもなオオイエバエ属ではありますが。 >> イエバエ科のなかには,○○ハナバエというのも多いですし;^_^) この辺は篠永先生や、晩年の加納先生が、ほぼ修正されましたね。みんな○○イエバエになりました。一時期イエバエ上科の中の科の範囲がなかなか確定しなくて、和名がついた時期にはハナバエ科に入れられていたようですね。Fauna Japonicaの執筆時期にはこの問題が解消されてある程度時間が経過していたのですが、にもかかわらず修正されていなかったのは、和名の安定性を乱すことを懸念されたのかもしれません。 |
- Joyful Note -
- Antispam Version -